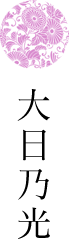2025年02月19日大日乃光第2425号
臍下丹田に、今一つ力を込めて佛様の試練を乗り越えよう
『三毒』の鬼を祓った節分豆まき
皆さん、ようこそお参りでした。 今日二月三日は「春を立てる」と書き、新たな一年の運勢が始まるという「立春」です。 そして昨日の、二月二日の日曜日は「節分」でした。奥之院では十一時と十三時の二回に亘り、開運豆まきを執り行いました。
節分に当たり、蓮華院では「心の中の三つの鬼を退治する事」をいつも伝えて来ました。 赤鬼・青鬼などの鬼を佛教では「貪・瞋・痴」の鬼と言います。
自分のものではないのに欲しがる貪りの心(貪)、不必要で理不尽な怒りの心(瞋)、そして物事の道理の分からない無智な心(痴)。 この「貪・瞋・痴」を『三毒』とも言い、この代表的な悪い心が鬼なのです。 そして自分の心の中に居るこの三つの鬼を抑え、戒めるための豆まきなのです。
「この福豆は隣に拾えない人がいたら分けてあげて下さい」とか、「持って帰られたら『これは福豆ですよ』と近所の人に分け与えて下さい」と伝えています。 これを「分福」と言います。
この「分福」を含め、「惜福」「分福」「植福」という三つの心掛けを述べたのは明治の文豪、幸田露伴です。彼は『努力論』という書物の中で、「幸福三説」を唱えました。
故米長邦雄永世棋聖との出会い
この「幸福三説」との最初の出会いは、故米長邦雄永世棋聖との運命的な巡りあいがきっかけでした。 それは今から三十二年前の平成四年九月十八日の事でした。 私はその日、総本山西大寺に当山の住職の認証書を受け取りに行く途中でした。
七月八日の先代真如大僧正様の御遷化に伴い、当山の第三世貫主を拝命し、御本尊皇円大菩薩様の御指示により「三年籠山」を決意して、まだ二ヶ月ほど過ぎたばかりでした。
その時は管長猊下から直接認証書を拝受する事になっていて、日帰りで本山に向かいました。加えて八千枚護摩と求聞持法を伝授して下さった方の、何度目かの八千枚護摩行の結願日でもありましたので、本山からの帰路の途中で、その方のお寺にお参りする事にしていたのです。 そういう経緯で例外的に外出したその日に、米長氏と巡りあったのでした。
鑑真和上が取り持ったご縁
当時、米長氏は名人位以外の多くの棋戦のタイトルを獲得しておられましたが、名人戦には六回挑戦して尽く敗退されていました。
その年、米長氏は意を決して、鑑真和上の足跡を訪ねる旅に出ておられました。鑑真和上が七度目の渡海でようやく日本に着かれた鹿児島県の坊津(ぼうのつ)から奈良の唐招提寺へと向かわれる途中で私と巡りあったのです。
その後、米長氏は唐招提寺の御影堂で鑑真和上の像と対面されて、強い啓示を受けられたという事でした。 その意味では、米長氏にとっても私にとっても互いに特別な日に巡りあうべくして巡りあったのかもしれません。
大阪空港から難波までのリムジンバスの中での三十分程の対話の中で、私が四十歳という若さで図らずも住職になった事を話すと、 「四十歳はもう若くはありません。将棋界ではすでに降り坂です。私は来年で五十を数えますが、今年は何としても名人戦で勝ちたいと念願しています」 と言われたのです。その後、 「十一月二十九日に熊本に行きますので、是非あなたのお寺に伺いたいものです」 と言われ、実際にその日に当山にお越しになりました。
名人戦玉名対局の舞台裏
米長氏はその後、名人戦の予戦を激闘の末勝ち上がり、名人への挑戦権を獲得されました。そして何度も苦杯を嘗めてきた中原誠名人を相手に、見事四連勝して念願の名人位に就かれたのでした。 この間、私は何度も文通で励ましました。
明けて平成五年の一月十五日、米長氏は今度はご家族連れで、晴れて名人として当山にお参りされました。その時私が、 「どうすれば玉名で名人戦を開催出来ますか?」とお尋ねした所、 「ご恩返しに私が協力しましょうか?」 と返して頂き、平成七年の四月十八日・十九日に奥之院を舞台として、当時の羽生善治名人と森下卓八段による名人戦第二局が実現したのでした。
このような経緯で、故米長氏には地域興しの一環としても、将棋寺子屋合宿をはじめ、たいへん有難いご尽力を頂戴したのでした。 その米長氏が現役時代に座右の銘とされていたのが、幸福三説の中の「惜福」でした。 私も交流の中で、色紙を頂戴した事がありました。
幸運を大切に活かす「惜福」
さて、「惜福(セキフク)」とは、自らに与えられた福を取り尽くしたり、使い尽くしてしまわずに、「天に預けておく」という事です。そしてその心掛けが、再度幸運に巡りあう確率を高めると、露伴は説きました。 恵まれた幸運を使い尽くさずに、惜しみながら大切に使う事によって、その恵みを存分に活かす事が出来るのです。
例えば二人の兄弟がいて、同じ様に新しい服を買って貰ったとします。 兄の方はその服を気に入って、普段着にしました。すると大切な時には既に傷んでしまい、晴れ着になりませんでした。 一方、弟も同じ様に服を買って貰いましたが、大切にしまって、日頃は古い服で我慢しました。すると大切な時に、大事にしまっておいた服を真新しい状態で着る事が出来たというわけです。
私達の世代は、正月になると服や靴を親に買って貰い、とても嬉しかった思い出があります。そういった意味で、この「惜福」の例え話は、実感としてよくわかります。
布施の心で分かち合う「分福」
次が「分福(ブンプク)」です。 「分福」とは、幸福を人に分け与えることです。自分ひとりだけの幸福はありえない。周囲を幸福にする事が、即ち自分の幸福に繋がるという心掛けが説かれています。 これは「恩送り」や「情けは人のためならず」に近い考え方と言えます。
お盆の時期にお伝えして来た目連尊者のお母様の佛教説話のように、恵まれた幸運を自分だけや、身内のためだけにひとり占めするのではなく、他の人にもお分かちする心掛けが大事なのです。 福は人に分け与えるほど、巡り巡って自分の所に返ってくるのです。皆さんも出来るだけ「分福」に心掛けて下さい。
信者の皆さん方の慈悲行のご奉仕や「一食布施」などの浄財の募金も、それを元にれんげ国際ボランティア会(アルティック)のスタッフが行っている難民救済事業なども「分福」の一環です。
この様な「布施」の心で周りの人々と福を分かちあうことが「分福」であり、「惜福」からさらに一歩踏み出して、人が幸せを実感し、広く周りを幸福にする方法なのです。
見返りを求めない「植福」
そしてその「分福」からさらに進めた幸福への道が、「植福(ショクフク)」です。 「植福」とは、将来に亘って幸せであり続けるように、今から幸福の種を蒔いておく事、精進(正しい努力)し続ける心掛けの事です。
過去に自らが蒔いた種が芽を出し、今の自分を形作っています。過去を書き替えることは出来ませんが、今から良い種を蒔き苗木を植え続けていけば、望ましい未来に繋ぐ事が出来ると、露伴は説いています。 「幸福三説」で説かれた三つの心掛けの中でも、露伴は「植福」が最も優れていると述べています。
たとえ自分は報われなくても、後世のために良き種を蒔き、苗を植えて行く。 良き習慣を家庭の中に定着させて行くなど、未来への長い視点で人々を幸福に導く究極の道が、この「植福」と言っても良いでしょう。 先に述べたアルティックの活動は「分福」であり、また「植福」でもあるのです。
自分を磨いて分福に努めよう
節分の豆まきという行事一つとっても、参加する人の考え方次第で、自らの福を他人に分け与えるという「分福」の良い練習になると思います。 これを一つのきっかけ、佛縁として、皆さんも皇円大菩薩様の御遺徳を、周りの人達に少しでもお伝えし、御利益の福を周囲に分け与えるように努めて頂きたいと思います。
そのためにも、自分自身が周りから信頼されるような人になる事を目指して下さい。 周囲の人から尊敬され、愛される様な人間になれるよう努力して下さい。 そうして他の人に「分福」、福を分け与えて頂ければ有難いと思います。
苦難とは力が均衡している状態
さて、十日に一度のこの法話ですが、今日はこれからするお話を家に持ち帰り、家族の間で実践して頂きたいと思います。 それは、人生には一見、乗り越え難い壁や、耐え難い不幸などがあるように思ってしまいがちですが、実際には越えられない壁など無いという事です。
どういう事かと言えば、例えば様々な偉人の伝記などを読み進めて行くと、その人の偉大な実績は、それが偉大であればあるほど、より大きな苦難や不幸、どうしようもない不運などが襲いかかってきて、それをどうにかして乗り越えた結果だと結論づける事が出来るからです。
これに関連して、最近読んだある書物に興味深い話がありました。 物理学には作用反作用の法則(運動の第三法則)があります。押した分だけ反発が返ってきます。 その著書によれば、人が非常につらい状態、困難に直面している状態は、この静止している状態に相当するのだそうです。
止まっている時の作用と反作用は同じ力、百対百で拮抗しています。そこにもし、ごく僅かでも押す力が勝れば、壁は倒せるのです。
壁にしても、不幸にしても、不運にしても、様々な障害というものは、必ずその人に見合う重大さであったり、危険度であったり、その人が耐え切れる範囲でしか来ないのです。
ですからそこでいま一歩、もう少し、ほんのひと握りの努力、一瞬の気を入れるのが大事な事なのです。それによって苦難に打ち勝つ事が必ず出来るという話です。
乗り越えられない試練はない
確かに不運の中で人は落ち込むものです。 大変苦しく辛いと思います。 けれどもそういう苦しい時には苦しみを味わいなさいと。苦しみに負けずに、それをじっくり味わえば良いのだと。そして苦しみそのものを生活の一部として、そのままに生きていけばいいんだと。 そうやって腹を据える、腹を括るという事が肝心です。
お腹のこの辺り、臍の下を「臍下丹田」と言います。まさにここに力が入るか入らないかによって、その人が今の止まっている状態、マイナスの力に抗って何とか踏ん張っている状態から、あとほんの僅かでもプラス側に頑張れば必ずや克服出来るのです。
この話を読み、「確かにそうだなあー」と思いました。 落ち込む時には落ち込んだ方がいい。その時の自分の心情を味わって、そこからまた立ち上がればいいのだと。 そしてその人にとって絶対に乗り越えられない苦難は、決して来ません。
今、苦しい…、今辛い。 そうしたら今までよりも一回でも多く「般若心経」を唱えたり、一回でも多く御宝号を唱えてみましょう。 今、耐え難いけど頑張っている。止まっているようだけれども、これはプラスとマイナスの力が釣り合ってる。 そこに今よりも少しだけ良い習慣を始めるとか、少しだけ思いを前向きにするとか、そういう事で苦難は乗り越えられるのだと確信します。
乗り越えられない苦難はありません。 それはその人に見合った、その人を成長させるために佛様が与えて下さった試練であり、それを乗り越えた時に私達は一つ成長し、一つ殻が剥け、一つ前に進んで行き、一つ世界観が広がるのです。
生きる意味や価値、生き甲斐など、そういったものに向かって少しずつ前進する。到達して行けるのだと私も信じています。 それを日々実行して行かなければならないと思いますし、皆さん達に対して、私自身がそういう姿を示し続けなければならないと思っております。
どうか春分の日の今日、運勢の変わり目を境に、今までやって来なかった努力を一つ足してみて下さい。今までやって来なかった良き習慣を一つ始めて下さい。
そして今ある福を大切に惜しみ、今頂いている幸福、今頂いている喜び、そういったものを少しでも実感して味わい、それを足場にして新しい習慣、新しい思い、新しい決意。そういう事を始めて頂けたら有難いと思っております。
今日も最後まで真剣に聞いて頂き、有難うございました。合掌
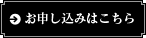
大日新聞(月3回発行)を購読されたい方は、
右の「お申し込みはこちら」からお申し込みいただくか、
郵送料(年1,500円)を添えて下記宛お申し込みください。
| お問い合わせ |
〒865-8533 熊本県玉名市築地玉名局私書箱第5号蓮華院誕生寺
TEL:0968-72-3300 |