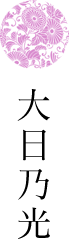2025年03月07日大日乃光2427号
先祖供養と家庭教育から日本の文化を再生しよう
皆さん、ようこそお参りでした。 寒い日が続いておりますが、春はもう目の前に来ています。十日に一度の法話ですが、なるべく皆さんの心に残るような話をしたいと願っております。
今日は日本人の高いモラル、道徳心についてのお話を致します。
三つの国でモラルを試した番組
イギリスのあるローカルテレビ局が、日本とフランスと中国を対象に、ある実験を行ったそうです。 それは、その国の街角で撮影スタッフがわざと財布を落とした時に、周りの人々がどんな対応をしたかの調査でした。
まず日本ではほぼ百パーセント、誰かが拾って「落としましたよ」と持ち主に返してくれたり、追いかけて渡してあげました。拾った人が持ち主に気付かなければ交番に届け出たという事です。 その様子を観て、番組では日本人は正直で道徳心が高いと賞賛したそうです。
花の都、フランスのパリで同じ事を試みた所、何と半分も持ち主の元に戻らなかったそうです。移民政策の影響で、EUではモラルの低下が問題になっている昨今、その一環でしょうか、拾っても届け出る事が少なかったと。 番組ではイギリスで同じ事をやっても、同じような結果だろうという反応でした。
最後に中国。北京や上海などの大都市では少しは持ち主に戻ったそうです。大都市には当局の厳しい監視の目があります。しかし地方では百パーセント近くが返らなかったという事です。 つまり日本ほど治安が良くて、安全・安心な国はないという事です。どこで落とし物をしてもほぼ返って来ます。
地方の無人販売所では、それこそ店員も誰もいない、お金を入れる箱だけ置いて、値札を付けているだけのお店が成り立っています。こういう事が出来ているのも、世界で日本だけだと、ある世界的なジャーナリストが言っていました。
日本を激賞したラムザイヤー教授
さて、皆さんの中にアメリカのハーバード大学のジョン・マーク・ラムザイヤー教授をご存知の方はおられるでしょうか? この方は数年前に、いわゆる従軍慰安婦問題について、当時の資料に基づいて「あれは商行為であり人権侵害ではない」と完全に実証された方です。日本にとっては有難い事でした。一方でラムザイヤー教授自身は韓国側から様々なバッシングを受けたそうです。
このラムザイヤー教授はアメリカのご出身ですが、ご両親に連れられて宮崎県で育ち、十八歳まで日本で暮らしていたそうです。 教授は今、ハーバード大学で名物教授になっておられて、受講生が沢山集まる中で、講義内容の質疑応答をネットに公開されているそうです。
それによれば、『日本人は人類が築き上げた最高の精神を持っている』と絶賛されているという事です。 先のイギリスのテレビ局による三つの国のモラルについての比較検証も、ラムザイヤー教授が仰るように、日本人の倫理観が世界でも跳びぬけて高い事の一端を表していると言えるでしょう。
このような情報は他にも沢山あります。 インターネットは情報の質において、確かに玉石混交ではありますが、日本は素晴らしいという話は世界中から沢山上っているのです。
子供を「羽ぐくむ」日本の家庭
ところでこういった、日本人が高度な倫理観、素晴らしい公徳心を持っている原因は何だろうかと、私なりに考えてみました。 一番最初に浮かんでくるのは教育の事です。
皆さん方もかつて子育てした思い出があるでしょう。その時どういう思いで子供を育ててきたか、無償の愛を注ぎながら、少々ぐずっても「まぁまぁ…」とあやしながら優しく育てて来られたと思います。 (若い信者に対して)あなたもご両親から優しく、愛おしく育てられた事でしょう。
教育の「育」(イク)という漢字を、日本語では「はぐくむ」と訓読みします。これは親鳥が卵や雛鳥をその羽毛で優しく覆い、温めたり風雨などから保護する様子を見て「羽ぐくむ」と読みあげた言葉なのだそうです。 そういう家庭における「育み」が子育ての原点なのです。
さらに学校では、教室や廊下を自分達の手で清掃するという習慣があります。給食でも当番を決めて自分たちで配膳します。 この様子を知った外国の方から、この習慣はとても素晴らしいと注目されているのです。 これは学校生活を家庭生活の延長として、清掃を習慣として定着させているのです。 ですから日本中どこに行ってもゴミが落ちていないのが普通です。
国際試合のサッカー場などを清掃して帰るのは、世界で日本人だけです。 そのように素晴らしい道徳心や、公徳心。 その原点は、人様に迷惑をかけないようにしようと家庭で育てあげている環境です。
先代真如大僧正様もよく教育について御法話をされました。長年PTA会長を務められ、少年研修館を始められ、子供達の合宿等、そういった事に非常に熱心でした。 ここで真如大僧正様が、教育の「育」という文字を題材に御法話された時の文章を、『大日新聞』昭和五十八年五月一日号から抜粋してお伝え致します。
教育の育という字を分解すれば子を逆さまに衆に付く
教育の「教」は、生きていく上に大事な、人間としての心がまえ、心の持ちかたを教え躾(しつ)けていくもの、と二千年前の先哲は教えているのです。
だから、ただ、物ごとを「知る」とか「知識の集成」だけではなくて、ほんとうは「尽す心」がそれ以上に最も大事なんだということをしっかりと知って下さい。
それでは、教育の「育」は何だろう?… 私は、これも又、辞書を引いてみました。 「育」とは、①そだてる。養って善をなさしめる。ひきいて徳をなさしめる②そだつ③やしなう、とありました。
しかしその「字解参考」を読んで、これまた驚いてしまいました。 「育の字、 ・月に従う。 は子を倒にした字なり」 と書いてあります。またしても「判じもの」(謎解き)です。 しかも育は本来「肉づきへん」なのに、なぜか「月偏」の「月」になっています。 今私たちは「育」の上の部分を「 」と書きますが、 「横一棒の中央の高いところからカタカナのムを書き、その下に月を置く」 という書き方が「育」のモト字というのです。
( ) でも「 は子を倒にした字なり」とは一体何のことでしょうか? 私は、紙に「横一にム」の字を大きく書いて、上から見たり下から見たり、右から左から、横にしたり裏返しにしたり、ためつ、すがめつ、悪戦苦闘いたしました。 わからないままに、小用に立ち、帰りしなに遠くから机の上のその字を見た時「ハッ」と思ったのでした。 上の方から逆に見ると、それが「子」の字に見えなくもありません。私は「ヤッタ!」と一人で喝采を叫んだのでした。
「倒にした」とあるのを私は「ヨコにした」とか「タオシタ」と読んでいましたが、実はこれは「サカサマにした」と読むのだということを知ったのはその後のことでありました。
さて次に、「 ・月に従う」とは一体何でしょうか。 月とは星月のいわゆる天体の月の外に、何か別の意味でもあるというのか。 いまさら「月」を辞書でひくこともあるまいとは思いましたが、ものはついでと意地になって引いた私はこれまた驚きました。
「月は太陰の精、地球の衛星」と出ているのからはじまって、いろいろと書いてあります中に、 「月は人道では…衆に配す」とあり、又、「月は臣の象(かたち)なり」と書いてあるのでした。
驚いた私は、「月は衆なり、臣の象なり」というのなら「日」には一体何と書いてあるだろうか、と或る期待で「日」を引いてみました。 もちろん、「にちりん。太陽」とあるのは当然でしたが、案の定「日は人道では…君に配す」「日は君の象(かたち)なり」と出ておりました。
結局「日は太陽なり、日は天子なり、日は君なり」というのに対して「月は太陰なり、月は大衆なり、月は臣なり」ということになるようです。
「日は天子で、月は大衆」 このように的確に示された私は、なるほどと今さらながら、思った次第です。 そうなると、先程「 ・月に従う」とあるのは、子をさかさまにして、足を持ってぶら下げ、大衆になじむように…相手のことを思いやり、みんなの中に溶けこんでいく庶民に育つように…、そのように、 「無理にも月(衆・大衆・一般社会の人々)に従わしむるように育てよ」 というのが、教育の「育」の字を造った先哲の考えであり、願いであったと思うのであります。
即ち、天子として育てるというのではなくて、大衆としての一個人、大衆の一人、庶民として生きていくように育てるというのです。 エリートとして育てるのではなくて、大衆になる為の育て方、それがこの字の考えであり願いであったということを、いままざまざと考えさせられているところです。
もちろん二千年前のそのままでは進歩がないかもしれませんが、それを土台にそこから出発する、しかも庶民としての出発というところに心を置いて子供の教育をもう一度見直すと同時に、育てかたを反省し、そして自分自身も、 「私は先祖代々の願いを生かしているか?」 「心を尽しているか?」 と反省する事でありましょう。 (引用終わり)
「育」を喝破された真如大僧正様
この『大日新聞』誌上で、「上述の推論は誰に聞いたでもなく、誰の本に依るでもなく、ただ『大漢和辞典』と遊びながら出した私の独断と偏見である」と真如大僧正様ご自身は謙遜されています。
また『大漢和辞典』より後の時代の考古学的発見や学問の進歩により、「育」の一文字についての定説も、年々変わって来ています。 しかし敢えて、「育」の「月」の部分を独自に「大衆」と解釈された点に基づき、決してエリートの育成が教育の目的ではないという先代の並々ならぬ強い信念の現れを今改めて窺い知る事が出来、また思い至るものであります。
その点で、たとえどんなに学問が進歩しようとも、そこに込められた先代の「教え」そのものは決して古くなる事などない、一人の宗教者、教育者としての不動の信念を見出し、改めて実感する所であります。
伝統を形作った二つの願いとは
明治時代の女性探検家・旅行家のイザベラ・バードから、現代のラムザイヤー教授に至るまで、日本を訪れた外国人は、「日本ほど子供を大切にする国はない」とか、「日本ほど子供が活き活きしている国はない」、「日本ほど正直な人々の住む国はない」等と評価してきました。
そして、日本に住む人々が一体何を大切にして生きてきたのかも記録されています。それは人のために役立つ事をしようとか、義務を精一杯果たそうといった、そういう精神性を抱きながら生きてきたという記録なのです。
外国から賞賛されている日本の文化や道徳心の高さ、そういったものを育んできたのは先代が仰られたように市井の中の各家庭における教育が土台であり、決して一部のエリート達によるものではなかったのです。
日本では昔から、「人様や世間の役に立つ子に育てたい」とか、「人様に迷惑をかけない子に育てたい」と、必ずこの二つを思って子育てしてきました。この二つの願いを全ての親が持って、育んできたのです。 これが日本の文化を形作り、また高いモラルを支えてきた素晴らしい伝統なのです。
ですからその子供を育てる学校教育のあり方も、世界から注目を集めて大きな反響を呼んでいます。日本そのものに対しても、非常に高いレベルの国際的な信頼があります。 そういった日本の良い面の全ての原点が、それぞれの家庭における教育と子育てであり、それを学校教育が受け継ぎ、地域も一緒になって支え、その上に今の平和で安全な日々があるという事を、どうか理解して頂きたいと思います。
佛教と神道に育まれた日本の文化
こういった事を考える上で、もう一つ忘れてはならない事は、私達日本人がご先祖様を大事にして来た事です。そこには両親、祖父母、曽祖父母、子や孫、曽孫といった命の縦の流れを重んじる精神性です。 日本人ほど、ご先祖様を大切にする民族は他にはないと思います。
また日本人は太陽と大地、海や川や森、暮らしを取り巻く自然の循環や恵み、そういったものに神様を見出してきました。 そしてご先祖様達が築き上げてくれた今の恵みに思いを致し、今の暮らしの豊かさに有難いと感謝をしてきました。
自然からの恵みと、先祖からの恵み、そういった縦と横の二つの精神軸を形作ったのが、日本の神道でした。 そこに招来された佛教が神道と融合し、「神佛習合」の形で、先祖供養の大切さが様々な教えの中に取り入れられ、人々の生活のレベルまで深く根を下ろして行きました。 人類史の中でも、こういった二つの宗教に育まれた文化は他に類を見ません。 これが実は日本の精神文化を形作っているもう一つの原点だと思います。
自然に対する感謝とご先祖様への感謝。それを基に各家庭の中で、人の役に立ち、人に迷惑をかけない子供を育てていく。 昔から続いてきたこの最も根源的な日本の伝統、その再生こそが日本を今一度雄々しく蘇らせる第一歩となるのであります。合掌
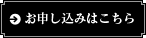
大日新聞(月3回発行)を購読されたい方は、
右の「お申し込みはこちら」からお申し込みいただくか、
郵送料(年1,500円)を添えて下記宛お申し込みください。
| お問い合わせ |
〒865-8533 熊本県玉名市築地玉名局私書箱第5号蓮華院誕生寺
TEL:0968-72-3300 |