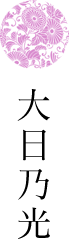2025年03月18日大日乃光第2428号
三月三日の桃の節句に当たり、国際協力の四十五年を振り返る
信者の皆さん、ようこそお参りでした。 今日、三月三日は「桃の節句」です。女子の健やかな成長を祈る年中行事の一つです。皆さんはかつてひな祭りをした記憶とか、お子さんやお孫さん達のためにお祝いした事を懐かしく思い出していらっしゃるかと思います。 しかし近年は、こういった昔ながらの伝統行事やお祭りなどが次第に薄らいでいる様に感じるのは私だけでしょうか?
「同胞援助」と「一食布施」を提唱
さて、この三月三日は蓮華院にとっても、信仰的にとても大切な日付であります。 今から四十五年前の昭和五十五年三月三日、当時マスコミで盛んに報道されていたカンボジアでの大量の難民発生に際し、先代貫主真如大僧正様は「大乗佛教僧侶の一人として、これを見過ごせない」と、カンボジア難民への募金を「同胞援助」と称して、この法座から呼び掛けられました。
それは大乗佛教の基本理念の一つである、「菩薩行の実践」という精神に基づく奉仕行の一環でありました。 菩薩行とは、たとえ自分自身が苦しく辛い境遇にあったとしても、さらに苦しく辛い状況にある人々に対して、出来る限りの奉仕を実践する事が、その要諦です。
そしてその募金活動に「同胞援助」と名付けられた事が、この募金が単なる一過性のものに終わらずに、一つの運動となって今日まで続いている大きな要因にもなりました。それは、世界中で困難な境遇にある人々を、私達と同じ同胞(はらから)と位置づけ、その苦しみや悲しみを同じ目線で自分の事として受け止める。まさに菩薩の同悲の心構えを持った活動へと繋がる出発点になったのでした。今日がまさにその日であり、そしてアルティック(ARTIC=認定NPO法人れんげ国際ボランティア会)が国際協力活動を始めて四十五周年という事でもあります。
さらに真如大僧正様は、同年十一月三日の奥之院大祭の御法話でもう一つ、「一食布施」の名の募金を提唱されました。この事によって、募金活動は体験と共感を伴う、蓮華院の信仰の大切な一部となったのでした。その日以来、カンボジア難民支援に始まり、タイやスリランカでの支援活動、ミャンマーでの学校建設支援事業などを推進しました。 そして令和二年以降、外務省の予算を活用する形での支援事業にも従事するようになりました。
ノルゲリン・チベット難民居留区
外務省による国際協力活動の一環に、「ODA」(政府開発援助)があります。 日本は、まだ戦後復興の最中であった昭和二十九年にODA拠出を開始し、早くも国際協力援助国となったのです。しかし政府主導による国際協力では、調査が不十分であったり、支援先の政府に一任される事も多く、インフラや建物などのハード的な活用に終始して、それらがその後実際にどう使われているかといった視点からは、あまり考えられていませんでした。
アルティックの様な民間団体(NGO)が世界を舞台に活動を推進して行く中で、政府のODAの手法について、疑問が寄せられるようになりました。 支援先の住民の目線に合わせていないのではないか等の提案をたくさん受けて、外務省と当時「国際ボランティア貯金」のあった旧郵政省が、様々な団体を審査して支援をするという試みが始まっていました。
インドのデカン高原のほぼ中央に位置するナブプールという都市の近くに、ノルゲリン・チベット難民居留区があります。 二十年前の平成十六年、アルティックが初めて郵政省の「ボランティア貯金」によってノルゲリンでの家屋改修事業に着手しました。 この事業は三年がかりで百八十七棟の家屋を改修するという内容でした。
このノルゲリン居留区での改修事業が全て終わり、落成式を迎えた時、村長のゴンボさんからアルティック宛に招待状が届いたのです。 その中には「ダライ・ラマ十四世法王猊下もご来訪されるので、是非ともお越しください」と書いてありました。
千載一遇の好機を掴むには
私自身は様々な事情で行けませんでしたので、私の名代として宗務長の光祐を任じ、久家君と真弘さんの併せて三人をインドに派遣しました。 そして、私から法王猊下への親書を託しました。親書には、翌年のアルティック創立二十五周年を機に、記念行事の特別ゲストとしてご来訪頂きたい旨を書きました。
このアイデアに、周囲からは「まさか、あり得ませんよ」「ダライ・ラマ法王と言えば世界のVIPですよ」といった声が上がりました。そんな周囲に対し、私は、 「しかしお願いしてみなければ、チャンスはゼロだよ。もちろんお願いしたからと言って、お越しになるとは限らない。しかし、お願いしなければチャンスはゼロなんだから」 と、私は一所懸命文章を考えて、それを翻訳して三人に託したのです。
その親書に目を通された法王猊下は、秘書の方と一言二言言葉を交された後、 「See You again.Next year!!」(来年再びお会いしましょう!!)と明快に、断定するように仰られて、当山へのご来訪をご快諾頂いたのでした。 現地の三人は目をパチクリさせて、「本当に世界のVIPのダライ・ラマ法王猊下が蓮華院に来る!?」と思ったそうです。
長きに亘る文化教育支援の賜物
ところで初期のアルティックの支援活動は、保育園・図書館・職業訓練や伝統文化の継承などの、文化教育面の支援活動が中心でした。 これはカンボジアでの難民キャンプにおいて、募金による浄財を元にした尊い資金をより有効に活用するためと、難民キャンプの人々は必ず帰国するか、第三国に移住する事になるので、民族の誇りと文化を継承するための文化・教育支援活動を行ったのでした。
ノルゲリン居留区での家屋改修事業より少し前の平成十三年から、アルティックではチベット亡命政府の教育省と協力して、チベット独自の文化を維持するためと、子供達の情操教育のために、チベット民話などから年間に三種類、九千冊の児童図書等の出版事業の活動を続けています。
また蓮華院本体からも、チベット密教の経典(全十八巻)を復刻し、一千セット発刊する事への全面資金協力をしました。 法王猊下は、蓮華院とアルティックによるこういった継続的な支援についてよくご存知でしたので、 「私が講演を行う事でアルティックの二十五周年に花が添えられるのであれば」 と、先の申し出にご快諾頂き、ご来訪の実現に繋がったのです。
ダライ・ラマ法王御来訪の意義
それから「ダライ・ラマ法王来熊歓迎委員会」を設立し、お寺の総力を挙げ、地域の叡智を結集し、労力の協力を頂きながら、万全の準備を整えて法王猊下をお迎え致しました。熊本県立劇場での国際協力シンポジウムの基調講演を初め、阿蘇神社への参拝、九州看護福祉大学での特別講演、奥之院での大法話会(約六千人)、アルティック二十五周年祝賀会、本院での世界平和法要という三日間の全ての日程を無事に終える事が出来ました。
皆さん、憶えてますか?もう二十年前です。 現在は池になっていますが、当時そこの五重塔の傍で護摩を焚いて、一緒にお参りしました。 当時、寺内的にはこれ程の大きな催しを実施した事は格別な意味がありました。 ともすると一過性のイベントとなり、内外へのアピールが不十分だったようにも思われましたが、それは一面的な感じ方でした。 目に見える大きな変化としては、これを機に、ダライ・ラマ法王猊下は、日本各地に毎年来日されるようになったのです。
さらなるODA事業への飛躍
アルティックではカンボジア難民支援に続いて、タイ国内のスラム街での支援、それからスリランカでの孤児院支援や大津波災害支援、そしてミャンマーでの学校建設事業へと展開しました。
ミャンマーでの事業には日本財団からのバックアップがあり、何と言っても平野喜幸君という傑出した人材のお陰で、学校建設を中心に地域興しから、先生達への教育支援に至るまで、まさに国際協力の最先端と言っても過言ではないような、非常に意義のある活動が出来たと思っております。
そして今、アルティックは外務省のODA、「日本NGO連携無償資金協力」(以下、N連と省略)という予算による支援事業へと進んでいます。 今、そのために凖教師の伊藤祐真さんが、小川幸さんという玉名市内在住の熱心で意欲的な新たなアルティックのスタッフと共にインドに行ってます。 このN連支援の始まりは、今から五年前の、ちょうどアルティック創立四十周年の節目の年であり、アルティックにとって画期的で歴史的な出来事でありました。
佛様の手に導かれてのN連申請
平成三十年にダライ・ラマ法王猊下を福岡の東長寺にお招きした時に、 「二年前に国会議員の有志の間で設立された「日本チベット国会議員連盟」(以下チベット議連)の事務局長さんから、『外務省の予算でチベット難民を支援したいので、長年チベット支援を続けている民間団体を知りませんか?』と尋ねられましたので、川原さんの所のアルティックの事をお伝えました」と、実行委員会のメンバーの一人が話されました。
その後、そのチベット議連の事務局長と連絡する内に、是非代表に会って欲しいとの事で、翌年の一月十七日に東京で面会しました。その会合の中で、チベット議連と外務省を繋ぐ担当課長さんのお名前を伺った所、何と数年前に「ミャンマー/ビルマご遺骨帰國運動」の中で巡り合った方でした。 この時、何か目に見えないお力に後押しして頂いている事を実感していました。
チベット議連の会長さんと事務局長さんとの会談の後、事務局長さんの秘書さんと、外務省の担当課長さんも交えて私達はしばし歓談し、先のN連に申請する事になりました。 その結果、まるで佛様の手に導かれるようにして、チベット難民に対する日本初の外務省ODAによる国際協力支援活動に、アルティックが従事する事になったのです。
信者の慈悲行あっての四十五年
これは信者の皆さん方の浄財により、二十五年以上に亘り、チベット難民への支援活動を継続出来た大きな賜物なのであります。 国内には他にもチベット人への奨学金を続けている団体等があり、また中国によるチベット人への人権侵害に対して声を挙げている団体もあります。しかし、具体的な支援活動を四半世紀以上に亘って続けている団体は、国内にはアルティックしかないのです。多くの団体では、せっかく始めても途中で続けられなくなって行きます。それは継続的な資金援助が困難だからです。 アルティックでは、蓮華院の熱心な信者さん達の信仰の一つの延長として、「反省」「感謝」「奉仕」の「三信条」の一環としての奉仕行、「同胞援助」や「一食布施」を実践して頂いています。
この基礎があってはじめて、民間団体としての国際協力の全てが出来ているのです。 偏に信者さん達の熱心な信心の発露の結果なのです。それが今に至る四十五年間続いたという、誠に稀有な有難い事であります。
国際協力の現場で学んだ「四摂法」
曹洞宗の教えの中に、「四摂事」という言葉があります。 これは人々を信仰に引き寄せ、佛法に引き寄せる四つの方法という意味で、「四摂法」とも言います。
第一に「布施」、人や社会に対して施す事。次に「愛語」、優しい言葉遣いで相手に接する事。そして「利行」、相手の役に立つ事をする事。そして「同事」、相手の傍に寄り添う事。 この四つはとても大事な事ですから、是非皆さん、覚えて帰って下さい。 「布施・愛語・利行・同事」です。
この言葉を初めて知ったのは、カンボジア難民キャンプで国際協力活動を始めた頃です。 現在のSVA(シャンティ国際ボランティア会)という日本を代表する曹洞宗の国際ボランティア団体の創設者で、事務局長を務めておられた有馬実成師から教わりました。 それ以来、常にこの「四摂法」を心に納め、特に国際協力の現場に於いて、日々実践に努めて行こうと決意しました。
家庭の中から「四摂法」を実践しよう
アルティックが行う国際協力の現場では、「四摂法」を、初めてお会いする方、縁もゆかりもない方々を相手に実践しています。ここにお参りの皆さん達は、「四摂法」を家庭の中で最も身近な人から始めて下さい。 人間関係における一番の根本は夫婦関係だと思います。親子関係ですら、元はと言えば、夫婦仲良く和合して初めて生まれるのが子供達ですから。人間関係、家族関係、家庭の平和の根幹は夫婦和合に違いありません。 これは佛教的な言葉を使わなくても、すぐに分かります。
ですから「四摂法」を、言わば夫婦円満の最大最高の秘訣にもなると思って日々実践して下さい。 夫婦お互い同士が慈しみの言葉を交わし、相手の事を思いやる。相手のために食事を作ってあげる。「今日は主人のためにどれほどおいしい料理を作ってあげようかな」「ひと工夫しよう」など、これは「利行」ですね。
お互いに愛の言葉で、まさにこれこそ「愛語」、愛の言葉を交わしあう。 そしてお互いに一緒にいる。傍にいてあげる。傍で励ます。「同事」。
この夫婦和合から始めて、家庭から地域へ、地域から国へと広げて行きましょう。 そして蓮華院では「同胞援助」など、世界の困った人達を同胞と見立てて、そういう人達のために一所懸命努力する事を始める。
そうやって信者の皆さん達が実際に、今まで四十五年間ずっと続けて来られた「慈悲行」の実践の一つが実を結び、その一端として世間から高い評価を受けて、新たな段階に至っているという事です。アルティック設立四十五周年のこの日に当たり、この「布施」「愛語」「利行」「同事」の「四摂法」を、これからも信者さん達と共に歩み続けて行きたいと願っております。 合掌
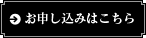
大日新聞(月3回発行)を購読されたい方は、
右の「お申し込みはこちら」からお申し込みいただくか、
郵送料(年1,500円)を添えて下記宛お申し込みください。
| お問い合わせ |
〒865-8533 熊本県玉名市築地玉名局私書箱第5号蓮華院誕生寺
TEL:0968-72-3300 |